
9月28日(木)夜
こんにゃくを買おうと、
会社帰り、牛込神楽坂のスーパーを覗く。
こんにゃくは、唐辛子で炒めようかと思った。
野菜売り場で、いんげん。
胡麻よごしでも作ろうか。
鯖が一本、切り身なっているものが、¥200程度と、安くなっていた。
相模湾産。もうそんな時期であるのか。
味噌煮でよかろう。
帰宅。
湯を鍋に二杯、沸かす。
この間に、いんげんを洗い、両端を切り、さらに半分に切る。
沸いた湯で、鯖の霜降り。
湯通し、で、ある。
鯖の湯通しは、どうするのがよいのだろうか。
文字通り、湯に入れ、湯通し、をすれば、沸騰した湯に入れて、
すぐ出しても、鯖は皮が柔らかく、はがれやすい。
箸で触るだけで、はがれてしまう。
笊の上にのせ、身側を上にし、湯をかける。
意図としては、ぬめり、を取る、と、いうことであれば、
これでよかろうか。
すぐに、流水ですすぐ。
魚の煮付けは、水からが基本、と、いう。
鍋に、水を張る。酒、しょうゆ少々、しょうがスライス少3〜4片。
点火し、熱くなってきたら、味噌を溶く。
味噌は、信州味噌3に対して、八丁味噌1程度。
味見をしながら、砂糖。濃い目。
煮魚は、昔は煮詰めるように煮るのがセオリーであったようだが、
煮る時間を少なくし、味を濃くする、最近は、これが主流。
味噌をよく溶き、弱火。
アルミホイルで、落し蓋。
煮過ぎは禁物。
ここから、6分。これは厳守しなければならない。
この間に、いんげん。
まずは、鍋に入れ、茹でる。
鍋に、すり黒胡麻を入れ、酒、砂糖、しょうゆ、気持ち水。
加熱。
煮詰め、味見。
これも、濃い目。胡麻も多目がよい。
ここに、茹でた、いんげんを入れ、和える。
OK。
鯖の鍋は、6分で火を止め、10分、味を馴染ませる。
最後に、こんにゃく、で、ある。
短冊に切る。
フライパンを加熱。胡麻油。
こんにゃくを入れ
酒、しょうゆ、砂糖少々、七味。
七味は多目に入れる。
濃い味と、辛さがポイント。
からめながら、煮詰める。
水分が少なくなり、こんにゃくに、しょうゆの色が付くくらいまで。
完成。
盛り付け。

食べる。
鯖。
魚のうまさ、というものは、特に煮魚の場合、
そのコラーゲンであるという。身に味の付くほど煮込むと、
コラーゲンが煮汁に出てパサパサになる。そこで、6分を限度とし、
魚本来のコラーゲンを身に残したままにする。
しかし、これだけでは味がないので、代わりに煮汁を濃くし、
煮汁をつけながら食う。
プリプリに、煮あがって、うまい。
いんげんも濃い目でよい。
ウイークデーに三品も作るのは我ながら、珍しい。
まあ、こんにゃくは、たいした手間でもない。
料理ともいえぬものだが、つまみとしても、簡単だが、うまい。
参考:「江戸のおそうざい」(八百善「料理通」280年の老舗が昔の料理本から
再現する江戸庶民の味)中央公論社「暮らしの設計」129号1989年第3版
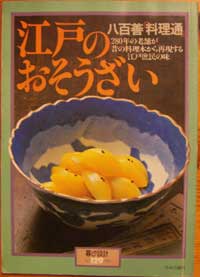
↑今さら紹介するのも、なんであるが、もう随分前、
10年以上も前になるであろうか、古本で買ったもの。
筆者も何回か書いているが、宮尾登美子の「菊亭八百善の人びと (新潮文庫)」
でも、知られている、江戸から続いていた老舗料亭、八百善。(料理教室)
その八百善のレシピが載っている雑誌。筆者の虎の巻であったもの。
今ではもう手に入りにくいかもしれない。
いんげんの胡麻よごしも、これから憶えた。