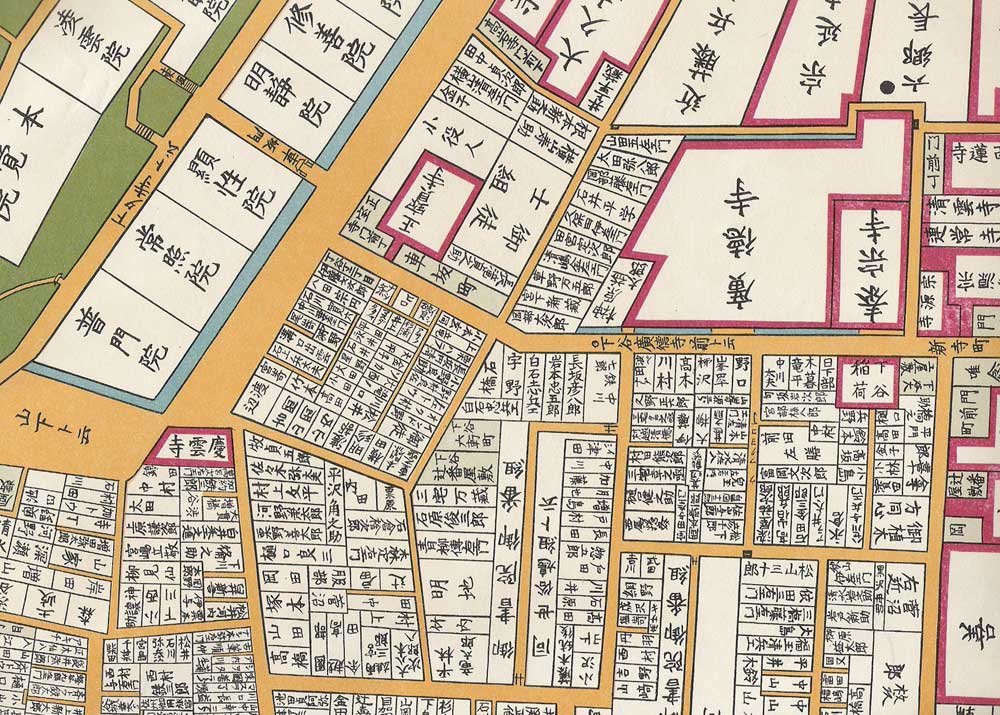今日は昨日の続き。
蜀山人大田南畝先生の後半生とその人生について考える。
*************
■第一回「学問吟味」受験。屈辱の落第。
寛政四年、南畝先生四十四歳の年である。
松平定信は、寛政の改革の一環として、幕臣の人材登用のための試験
「学問吟味」を、昌平坂学問所で行なっている。
これに、南畝先生は、若い幕臣に交じり、半白の頭で、
受験をしているのである。
むろん、成績は優秀であったのだが、この時は、
この試験の事務官であった、森山源五郎(孝盛)という者によって、
落第させられた。
この森山は、「平生(へいぜい)大田を憎悪し」
「人格の点で高級幕吏には不適格」(「大田南畝」浜田儀一)である、
というのが理由であるといった。
森山は、南畝先生と同様にこの時代、随筆家としても
数えられ、先生の名声に嫉妬し、落とした、という
噂も立った、らしい。
そもそも、なぜ、南畝先生は、こんな若者向けの試験を受けたのか。
積極的に、受けたのであろうか。
これには、まずは、御徒の組頭をはじめ、周囲の勧めがあったらしい。
先にも(昨日配信分)指摘をしたが、時代が変わり、筆を折った、
これは一つの選択肢として、わかる。
そして、しばらく、ほどぼりが冷めるのを待ち、また
書き始める、と、いう選択肢もあったのではないか、と、いう疑問である。
実際、この寛政四年以前にも人材登用令があり、
「この機会に南畝に期待する声は近辺にあるいは江戸中に高かった」
(前出・浜田)が
「『歩兵還(ま)た禄(ろく)あり、
笑うなかれ、儒と為らざることを。』
御徒の身分でも俸禄はもらえるから、別に儒者になりたいとは思わない。
どうか笑わないでくれ」(前出)。
と、いうことで、やはり、先生、受験などしたくなかったのである。
ひっそりと、暮らしていたかったのではなかろうか。
(ここでは、また書き始めたいかどうかは、おいておくとして。)
それ以前の、先生の名声、がそうさせなかった。
不本意ながら、人材登用試験を四十四歳にして、受けさせられた、
と、いうことだったのではなかろうか。
そして、嫉妬、嫌がらせによって、落とされた。
これはショックであろう。屈辱以外のなにものでもない。
江戸随一の花形知識人として名を売った先生が、受けたくもない
人材登用試験を若者とともに受けさせられ、挙句の果てに落とされた。
「ふざけるな!、もういい!」、と、筆者なら思う。
しかし、これが、「組織」というものである。
筆者も、四十を越した、サラリーマンである。
むろん、よくわかる。会社などでは、よくあること、で、ある。
出世できるかどうか、は仕事ができるか、ではない。
むろん、できなくてはだめだが、日々のつき合い、
様々なしがらみ、派閥、、その他色々、、。
そしてまた、「あいつは、ああいう奴だ」という、一度付いた
評判、特に悪評、というものは容易には変わらない。
これも組織という中では怖いことの一つであろう。
南畝先生の場合、田沼時代には、調子に乗って時代の寵児として、
ふざけた狂歌を作り、豪遊し、はしゃぎ回った男。
そして、真偽のほどはともかく、例の「ぶんぶ」の落首の作者とされた、
批判分子、そんなレッテルである。
南畝先生だとて「自分のしてきたことではあるが、
なんで、俺は、こんな目に会わなければならないのだ」と、
思ったはずである。
■やっと合格、そして任官、しかし、、甘くない。
そして、その二年後、四十六歳の南畝先生は、
第二回の「学問吟味」を再度受験し、今度は見事に、主席で合格している。
この二年の間に南畝先生に、なにがあったのかは研究書ではわからない。
童門冬二氏の「沼と川の間で・小説太田蜀山人」では、
先の、嫌がらせをされた、森山某に、親しい先輩の周旋で、
不本意ではあるが、詫びを入れた、という話にしている。
そういうことも、想像できなくはない。
しかし、この二回目の受験前後の、作(詩)をみると、
先生の心境には、なにか、“ふっきれた”様子がある。
よくわからぬが、ある種、諦め、の境地に達していたのかもしれない。
「俺が生きていくには、ひっそりとしていることも許してもらえず、
組織人として、頭を低く下げ、へこたれず、くさらず、前向きに生きよう。」
そんな心持であろうか。
表現者であり、花形知識人としてのプライドもあったであろう、
南畝先生が、ここまでの境地によく達したものである。
筆者などであれば、とうにくさって、投げ出しているのではなかろうか。
この試験の褒美で先生は、お上から、銀十枚をもらっている。
これを十九年前、御徒の役目で「日光御社参の時に
賜った弁当籠に収めて、蓋の上に銘を書いた。それには
「身歩兵に籍、業散儒に類す」−−御徒の職にありながら、
文筆三昧に耽ったのを恥じ、ここに賜銀を封じてみずから戒めるとある。」(同)。
洒落であろうか?これが本当に、本心であったのかどうか、、、。
さて、しかしで、ある。
合格したとはいえ、南畝先生、
その後しばらく、そのまま御徒を勤めさせられた。
勘定奉行配下の、支配勘定という役目を仰せつかったのは
やっと二年後、四十八歳の年。俸禄は、百俵五人扶持と、暮らしは、
やっと、少し楽になった。
この二年は、嫌がらせであろうか。
わからぬが、合格はさせたが、そうは、甘くない、ということを
示したかったのであろうか。
いやはや、たいへんである。
役目に付くと、南畝先生は、先に述べたような決心のもとか、
古い文書整理など、面倒な仕事もやらされるが、
前向きに着実に、与えられた仕事に励み、
事務処理能力も発揮し、成果をあげてもいる。
この真面目さはなんであろうか。サラリーマンとして考えれば、
適当に、可もなく不可もなくコナス、こともできたはずで、ある。
なぜ、であろうか。
この年で、出世したい、という欲がそれほどあったのであろうか。
あるいは、文人として名声を馳せた自分へのプライド、で、あろうか。
(小役人の仕事など、俺ならばチョチョイと、120%やってやるよ!、
と、いうような、、。)
または、正真正銘、幕臣としての責任感なのか。
(この文書整理でおもしろい歌をよんでいる。
『五月雨(さみだれ)の日もたけ橋の反古しらべ 今日もふる帳あすもふる帳』
文書整理は竹橋の倉での作業であったという。反古(ほご)は、古い紙。
「ふる(古)帳」は、「ふるてふ」で、
「(雨が)降るという」、の意。「今日も、明日も五月雨が降るという」 にかけている。)
ともあれ、その後、そこそこ、目をかけてくれる、上司もいたらしく、
勘定方ではよい役目とされる、大坂の銅座へ転勤などしている。
しかし、その上司がいなくなると、五十五歳で、長崎奉行所へ転勤。
これは左遷であったという。
そして、最もひどいのが、六十歳で玉川(多摩川)の巡視という役目
につけられた、ということであろう。
この時代であれば、六十歳など、よぼよぼの老人である。
羽田から八王子まで堤防の状態などを、それも真冬、四ヶ月間
徒歩で調査して回った。
結局、最初に貼られたレッテルは、
最後までついて回った、のであった。
南畝先生は、子息の病廃などもあり、隠居もできず、
亡くなる五年前の、七十歳まで役目についていたようである。
まったくご苦労様である。
幕臣としてはこのように、恵まれたとはとてもいえない、
いや、散々な人生であったわけである。
しかし、一方、文人としての南畝先生は、後半生、
さほどに悪くもなかった。
勘定方になった後、特に、長崎から後は、
大名などとの交際もあり、江戸はもとより全国で、
その名声は衰えなかったようである。
そういう意味では、狂歌作家の活動はやめていても、
スター性といったらよいのか、人をひきつけるものは、
最後まであったようである。
(それがまた、嫉妬を買い、齢(よわい)六十にして
多摩川っぺりを歩き回らせることになった、と、いう指摘も、ある。)
■南畝先生の評価?
さて、蜀山人 大田南畝先生、どんな人生だったのであろうか。
幕臣として、幕府の役人として、文人として、、これだけの波乱万丈。
幸せであったのであろうか。満足して冥土に旅立ったのであろうか。
正直にいうと、まだ、よくわからない。
先の童門氏は、南畝先生自身「満ち足りていた」、と締めくくっているが、
そうであろうか。筆者にはそうは思えない。
後悔はしていなかろうが、満足ではなかろう。
あったのは、諦観、であろうか。
(諦観を含めて、満ち足りていた、ともいうこともできようが。)
ただ、今、思うことは、残した狂歌の作品よりも、
表現者であり幕臣でもあった、大田南畝という人、
その人生そのものが、一つの作品のように思えるのである。
そうとしか、いいようがない。
それだけ南畝先生の人生には、魅力があると、思うのである。
では、狂歌師としての評価はどうであろうか。
これもみておかねばなるまい。
いわゆる文芸性、芸術性を問われると、
一般に昔から、さほど高くはない。
いわゆる、書き散らした作も少なくはないようである。
しかし、当時、江戸庶民が支持をしたのは、芸術性などではなく、
切れ味、の、ようなもの、で、あろう。
二、三、挙げてみる。
『金銀のなくてつまらぬ年の暮れ なんと将棋のあたまかく飛車』
「つまらぬ」は、「詰まらぬ」。将棋の詰むと、年が詰まる、
おもしろくない、意の、「つまらぬ」。
「なんと将棋」は、「なんとしょう」(なんとしよう)。
「かく飛車」、は、「角、飛車」。
駄洒落であるが、これだけ洒落ていれば、見事としかいいようがあるまい。
好き嫌いでいっても、筆者は好きである。
『月見れば千々に芋こそ食ひたけれ わが身ひとつのすきにはあらねど』
馬鹿馬鹿しいが、おもしろい。
『春がすみ立ちくたびれてむさしのの はら一ぱいにのばす日のあし』
これなどは、のどかで、よいではないか。
狂歌師、大田南畝の評価は、洒落て、粋で、切れ味のある、
落語などを生んだ、江戸化政文化の先駆けとして
間違いなく、大きなベースになっているといえよう。
しかし、そうした狂歌師としての評価より以上に、筆者は
先に述べたように、本当は、先生の人生そのものが
一つの表現作品として評価されてもよいのでは、と、思うのである。
狂歌の作品も含め、役人として再出発せねばならなかった後半生、
そこに至るまでの葛藤も全部込みで。
これだけ、ドラマチックな(幕臣)表現者としての人生は
そうそうないのではなかろうか。
後半生の役人としての人生も紛れもなく、表現者であるからこそ
生まれてきてしまった、ことだからであるし、受験やら、
それぞれのターニンングポイントで、選択をしたのも
表現者大田南畝自身であるから、筆者はおもしろいと思うのである。
(まだ消化不良である。前にも書いたが、
筆者がサラリーマンをしながらこんな文章を
書いているからであろうか。
わからぬが、煎じ詰めると、この人、なにか好きなのである。
はしゃぎ方が好きだし、屈折のし方も惹かれる。
もっともっと、掘り下げて、考えたい、
そんな思いにさせる大田南畝という人である。
また、別の形ででも、書いてみようかと思っている。)
************************
参考:大田南畝 浜田義一郎 吉川弘文館
:蜀山人の研究 玉林晴朗 東京堂出版
:沼と川の間で・小説大田蜀山人 童門冬二 毎日新聞社