
2月13日(水)
東京都美術館に「奇想の系譜展」を観てきた。
人気の若冲など、江戸時代の絵を「奇想」というキーワードで
つなげた展示である。
先日書いたトーハク「風神雷神図のウラ」の先達、師匠から
受け継いだ、正統な流れ(?)に対しての「奇想」といって
よいのであろう。
「江戸アバンギャルド」なんという言い方もあるが、
江戸時代のとんがった作品を集めているということである。
おもしろかった。
岩佐又兵衛、狩野山雪、白隠慧鶴、伊藤若冲、曽我蕭白、長沢芦雪、
鈴木其一、歌川国芳の8人のいわゆる絵師でない人もいるが、絵を
描いて残した人。
この順は時代順で、岩佐又兵衛(1578-1650)、狩野山楽
(1590-1651)、白隠慧鶴(1685-1768)、伊藤若冲(1716-1800)、
曽我蕭白(1730-1781)、長沢芦雪(1754-1799)、鈴木其一
(1796-1858)、歌川国芳(1797-1861)という年代。
岩佐又兵衛の江戸初期から歌川国芳の江戸後期まで江戸期全体に
渡っている。
それぞれ影響がなかったとはいい切れなかろうが、師弟関係のような
ものはないのであろう。
本邦初公開の作品もありまた、岩佐又兵衛、狩野山楽、白隠慧鶴、
の三人は私も知らなったが、なかなか観ごたえがあった。
知られていない、あまり今まで日が当たっていなかった
作家、作品が掘り起こされてくるというのは、よいことであろう。
まずは有名な若冲。
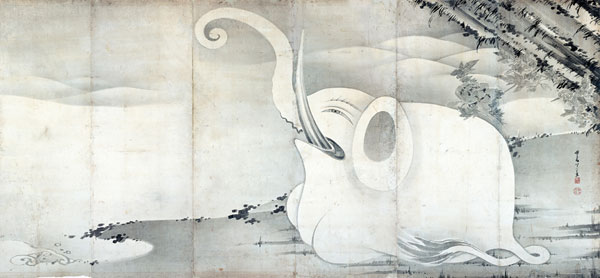
伊藤若冲「象と鯨図屏風」紙本墨画 六曲一双 各159.4×354.0cm
寛政9年(1797)滋賀・MIHO MUSEUM(部分)
若冲といえば、とにかく細密に描かれた鶏が有名で今回も
かなりの作品が鶏なのだが、こんなものもある。
象は若冲の作品では他にも観たことがあるが、これもなかなかよい。
右隻の象に対して左隻は大きな鯨。
彩色がないというのも、シブイ。
ファンタジー感も漂っている。
白隠慧鶴。
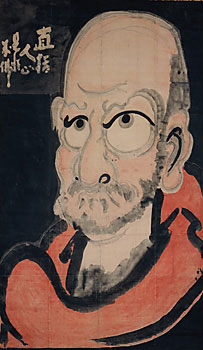
白隠慧鶴「半身達磨図」紙本着色 一幅 192.0×112.0cm
一幅 139.4×85.1cm 江戸時代(18世紀)
米国・エツコ&ジョー・プライスコレクション
この禅宗の坊さんは元禄の頃から田沼時代、江戸前期から中期の人。
生まれは駿河。
この人は、目であろう。
存在感が凄い。
漫画というのか、キャラクターともいえるような
タッチがおもしろい。
この系譜、全体にいえると思うのだが、浮世絵やその後の
漫画、アニメ、キャラクターだったり、やはり紛れもなく
正統とは別の我が国の表現の大きな流れといってよいのだろう。
それで現代の我々が観ても親しみやすく感じると考える。
この人にも触れておかなければ。
鈴木其一。


鈴木其一「夏秋渓流図屏風」紙本金地着色六曲一双
各166.4×363.3cm 江戸時代後期 東京・根津美術館
先日の「風神雷神図のウラ」の酒井抱一の弟子。
江戸琳派の真打などともいわれる人。
師の抱一が亡くなってから、弾けた作品を残している。
これ、なんだ普通じゃないかと思われるかもしれぬ。
琳派は先日の、風神雷神図だったり、燕子花(かきつばた)図だったり、
決まったものの様式美を追及しているといってよいのであろう。
だが、この絵のモチーフは、松竹梅でもなく、地味な山深い渓谷の檜。
そして、青、群青がドギツイほど目に飛び込んでくる。
国芳はまあ、私にはお馴染み。
作品としてのおもしろさはいまさら言うまでもない。
ただ、ちょいと余談だが、浮世絵の展示について
私は前から疑問に思っていることがある。
浮世絵というのは額に入れて壁に並べて鑑賞するものではないと
思うのである。肉筆画は別なのだが、浮世絵は元来、手に持って
(あるいは置いて)手元で観るものである。つまり至近距離で観るもの。
また版画である。初版であったりオリジナリティーに意味は
ほとんどなかろう。どうも美術館での展示の仕方に違和感を感じるのである。
(複製でよい。手に持って観たいのである。)
他の見せ方を考えてはいかがであろうか。
最後、岩佐又兵衛。

重文 岩佐又兵衛「山中常盤物語絵巻 第四巻(十二巻のうち)」
紙本着色 一巻 34.1×1259.0cm 江戸時代初期(17世紀前半)
静岡・MOA美術館
ちょっとわかりずらいが、細部をよく観るとなかなか
サイケなのである。浮世絵の源流と言われているのもさもありなん。
だが、ちょいと引っかかったのは、絵もさることながら、
この人そのもの。
あの戦国武将、荒木村重の子。
NHK大河「軍師官兵衛」で官兵衛が荒木村重によって1年間
有岡城に幽閉されたのを覚えておられる方もあろう。
有岡城は落ち、荒木村重一族は根絶やしにされるが、当時2歳の
又兵衛は乳母に救われ石山本願寺に保護、以後母方の岩佐姓を
名乗り成長する。
又兵衛というのは、いかにも戦国っぽい名前である。
そんな人が生き残っていたのかという感じである。
織田信雄の小姓になったりするが、信雄改易。その後、
京都で絵師になる。
大坂の陣後、あの結城秀康の子、福井藩主松平忠直に
招かれ福井へ。作品を多く残しているのはこのあたりのよう。
そしてさらに江戸に招かれ20年ほどすごし、73歳の長寿を保ち
没している。
戦国から江戸初期というのは、こういう人が随分いたのであろう。
この人の一生がドラマになりそうである。
ともあれ。
江戸期の絵画の層の厚さ、豊かさには驚かされる。
#東京都美術館 #奇想の系譜展