引き続き、落語とはなにか。
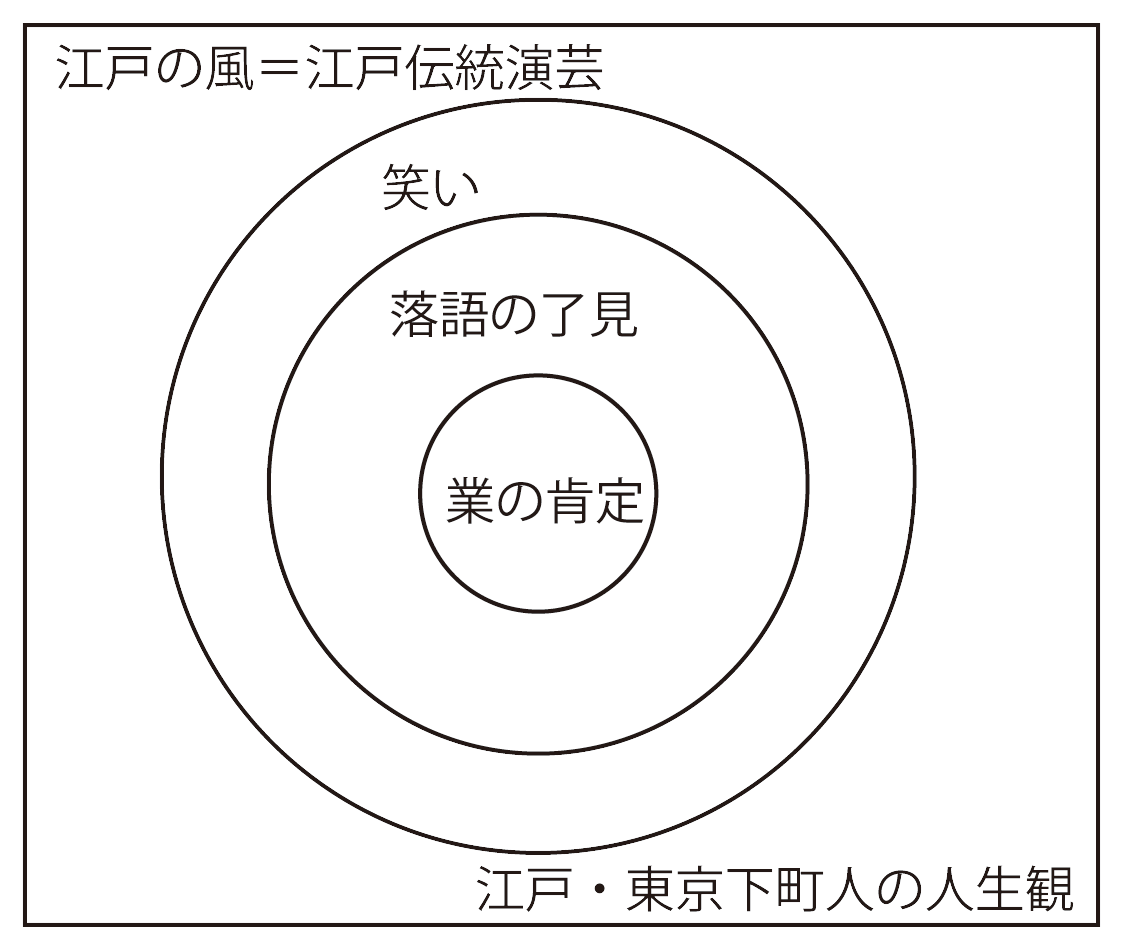
まだ、仮説であるが、落語を構成する要素の図、で、ある。
噺を一つ一つ、検証をしなければいけないが
談志家元の言っていた「業の肯定」あるいは「落語の了見」
こうしたものは構成要素の一つであろう。
で、まだ他にもあるであろう。
これは、今後の課題とさせていただく。
そして、昨日はこの図の上、一番外側に書いた
「江戸の風=江戸伝統演芸」について。
これがなければ、古典落語ではない。
これを演者は伝えたいから、お客は、これを聞きたい、
観たいから落語に接する。
落語がこの世の中にある意味として、重要な要素であると
いえる。
(まあ、これはだれにも異論はないと思われる。)
さて、今日はもう一つ、この図の下の方に書いた
「江戸・東京下町人の人生観」について、述べてみる。
これは、談志師匠がいっていたことではなく、
私が考えたこと、ではある。
ある意味、家元のいっていた「業の肯定」やら「落語の了見」やら
その他にもあるであろう、落語の各噺の中で語られる
ソフト的な構成要素、というのか、そんなものをまとめると、
こういうことになるのではないか、ということである。
ところで、江戸で落語が生まれたのは、いつであったか。
初代、山(三)笑亭可楽が下谷稲荷で初めて
寄席を開いたのが、幕末にはまだ70年ほど間がある1798年(寛政10年)。
その後、文化文政期、爆発的に落語は江戸で流行し、
寄席が100軒にもなっている。
可楽に加え、初代の三遊亭圓生、同林屋(家)正蔵などが
その主体。
初代可楽の始めた頃は、謎掛けやら三題噺で、現代まで残っている
江戸落語は、その後のこの文化文政期に生まれたといってよいようである。
(もちろん、その後に生まれた噺も数多くあるだろうし、
人情噺など多くの作品を残した、三遊亭圓朝は明治の人ではある。)
今、我々がイメージする“江戸っぽいもの”のほとんどは
この文化文政期を中心とする江戸後期にほぼ生まれて、花を開いた。
歌舞伎も初期の開花は、元禄であるが、東海道四谷怪談の
四代目鶴屋南北は文化文政期、白波ものの河竹黙阿弥は、その弟子。
浮世絵も最盛期は文化文政。
落語に流れている「人生観」はこの時期に固まったもの、
と、いってよいのではなかろうか。
で、これも仮説ではあるのだが、「江戸・東京下町人の人生観」
なのではないか、と、考えている。
では、それはどんなものなのか。
1999年でさほど、新しい著作ではないが、小林恭二氏の
『悪への招待状 ─幕末・黙阿弥歌舞伎の愉しみ』 (集英社新書)
というのを最近読んだ。
実はこれ、この10月、モルジブで、家元の『最後の落語論』と
前後して読んだのだが、なんとなく、シンクロするものが
あったのである。
小林恭二氏はこの本で、この時代の江戸人のことを
評して、前近代人とするには、成熟しすぎている。
近世人ではなく、近代人といった方がよい、というような
趣旨のことを書かれていた。
(むろん、小林氏は黙阿弥の芝居を下敷きにして、こういっている。)
一般に、江戸時代は近世、明治以降が近代と歴史では
定義されている。
これはむろん、欧米の尺度でいう近代と近世、である。
例えば、国家として考えれば、明治新政府の成立をもって
近代国家、と、いえるのであろうが、こと文化的な成熟度、
個人の人生観、人生哲学、などからいえば、江戸末の
江戸人は、前近代人ではもはやいえないのではないか、と。
落語の中に流れている人生観というのは、欧米流の
近代人とは違うものだが、前近代人ではない。
そうとうに成熟している。
小林氏の議論を読んで、その通りだ!、と
合点がいったのである。
私は談志家元の主張から学び、自分なりに考えても、
落語に流れている人生観というのはそうとうにすごいものだ、
と、前々から考えていた。
そうなのだ。
ひょっとすると、いや、間違いなく、欧米流の近代人などよりも
江戸末の江戸の町人文化は遥かに成熟しているすばらしい文化であり、
人生哲学を持っており、その集大成というのか、
それらが散りばめられているのが、江戸古典落語である、と。
いきなり、結論めいたことを書くと、読んでいる方には、
なんのこっちゃ、と、思われよう。
いずれ、順を追って、説明をしようとは思うのだが、
私自身とすれば、これだけで、江戸古典落語を守り、
若い人々に、そのすばらしさを伝える理由には、十分
なのである。
談志師匠に多大な影響を受けた者として
これは、この後も、肝に銘じて続けていこう、
と、思うのである。
と、いったところで、今日はここまで。
また明日。
